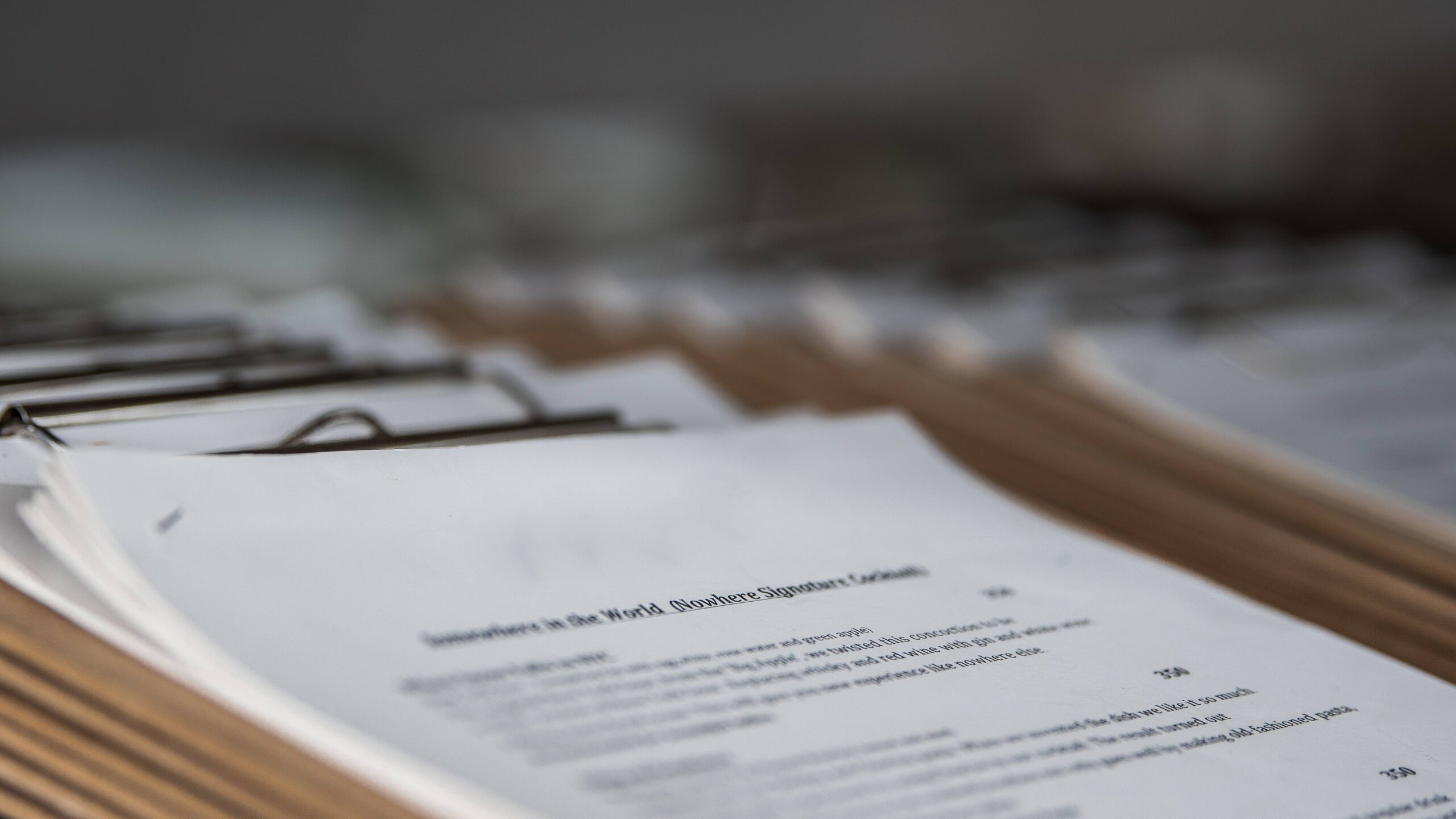この記事では、売掛金の時効とはどういったものなのかをはじめとし、売掛金が回収できなかった場合の対応や、時効が中断する理由にはどんなものがあるのかなどを解説します。
取引先と接する営業担当者の方も売掛金やその回収についての理解を深めることで、未回収のリスクを軽減することができるでしょう。

売掛金の時効とは?
売掛金とは掛売りによって生じたまだ回収していない代金で、売掛金を受け取る権利を売掛債権と呼びます。
この売掛債権には時効があり、定められた期間を超過すると債権が消滅してしまいます。これは「債権等の消滅時効」として、民法第166条に定められています。
売掛金の時効は5年です。2020年に民法が改正され、債権等の消滅時効は5年とされました。
民法改正前の売掛金の時効は2年だったので、2020年3月以前に発生した売掛金は2年、2020年4月以降に発生した売掛金は5年が時効となっています。
改正後の民法には次のように定義されています。
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
民法 第百六十六条| e-Gov法令検索
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
売掛金の場合、債権者は請求を持っていますから、「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。」にあたり、時効は5年となります。
関連記事
売掛金とはなにか 用語の解説と売掛金の回収方法について | URIHO BLOG
企業間取引の基本 掛売りとはなにかを解説 | URIHO BLOG
時効の起算日とは?
売掛金やその他の債権管理において、時効の起算日を正確に把握することは極めて重要です。時効の起算日とは、債権の時効期間が開始する日のことを指し、この日から時効期間が計算されます。時効期間内に債権者が債務の履行を求めなければ、債権は時効によって消滅する可能性があります。
時効の起算点には、主観的起算点と客観的起算点の二種類があります。主観的起算点は、債権者が債務の履行を請求できることを知った日から時効期間が始まるケースを指します。一方、客観的起算点は、債権者が債務の履行を請求できる状態になった日、すなわち債権が発生した日から時効期間が始まるケースです。
特に、支払期日が定められている場合、時効の期間は支払期日の翌日から発生します。例えば、ある取引の支払期日が2023年9月30日であった場合、時効期間の起算日は2023年10月1日となり、時効期間はこの日から数え始めます。時効期間が5年である場合、この例では2028年9月30日に時効を迎えることになります。
支払期限が特に定められていない契約においては、サービス提供完了日や商品の引き渡し日など、債権が発生した日が起算日とされます。
また、時効期間の計算においては「初日不算入の原則」が適用されます。この原則により、起算日となる日は時効期間の計算に含まれず、翌日が時効期間の第1日目となります。
このように、時効の起算日を正確に理解し、時効期間を適切に管理することは、債権の有効な行使と保護に不可欠です。債権者は、時効期間の管理に注意を払い、必要に応じて時効の中断や更新などの措置を講じることが求められます。

時効の援用とは
時効の援用とは、債務者側が時効制度を利用したいという意思表示をすることです。
時効が成立しても売掛金は自動的に消滅するわけではなく、債務者が「時効が成立したので売掛金は消滅しています」と債権者へ意思表示することで、売掛金が消滅します。
この意思表示を「時効の援用」といい、多くは内容証明郵便で債務者から債権者へ書面で通知されます。
売掛金を回収する債権者の立場からすれば、時効までに支払いを行わなかった取引相手から「時効制度を利用します」という意思表示を受けることになります。
時効の中断・時効の更新とは
売掛金には5年の時効がありますが、この時効の進行を一時的に停止や時効期間をリセットすることができます。
旧民法ではこれを「時効の中断」「時効の停止」と呼んでいましたが、民法改正後は「時効の更新」「時効の完成猶予」と定義されています。
時効の更新と時効の完成猶予は次のような違いがあります。
- 時効の更新:時効期間がリセットされること
- 時効の完成猶予:時効の進行を一時的に停止すること
また売掛金の時効の更新や時効の完成猶予が適用される主なケースには次のようなものがあります。
裁判上の請求/支払督促/和解または調停/破産手続きなど
上記の事由が終了するまで時効の進行を一時的に停止します。また、上記手続きによって権利が確定した場合は時効が更新され、事由が終了したときから新たに時効が進行します。
催告
催告を行ってから6ヵ月間時効の進行を一時的に停止します。催告とは債務者への督促を指し、法的な手段である必要はありません。
天災など
天災などによる障害が消滅したときから3ヵ月間時効の進行を一時的に停止します。
関連記事
督促とはなにか 催促との違いと支払督促のやり方をあわせて解説 | URIHO BLOG
支払い督促申立書とはなにか 手続きのやり方と記載項目の解説 | URIHO BLOG
債権の一部が支払われた場合、時効はどうなる?
売掛金には時効があり、更新や完成猶予が適用される主なケースを前述いたしました。
そのほかにも、債権の一部が支払われた場合にも時効が更新されます。
民法152条では次のように定義されています。
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
債務の一部を支払うことはこの権利の承認にあたるため、時効の更新が適用されるのです。
参考・引用元
売掛金の回収ができないとどうなる?
企業が売掛金を回収できず未回収になった状態を「貸倒れ」といいます。
貸倒れとは、企業の売掛金や貸付金の回収が困難となる状態を示し、これは主に債務者が返済能力を失った場合や経営不振、不良債権の増加などの要因により引き起こされます。貸倒れのリスクを低減するため、与信審査の厳格化や貸付条件の明確化が必要です。
貸倒れが発生した場合、企業は回収不可能となった資金の経済的損失を「貸倒損失」として計上する必要があります。
貸倒れにおける損失認識のタイミングとは
貸倒損失は、売掛金を回収できない、というだけでただちに損失として計上できるわけではありません。税法上、損失計上できるタイミングは決められています。
その理由は、自由に損失計上ができてしまうと、恣意的な利益操作を可能にし、租税回避に利用されてしまうからです。
売上が多く上がった事業年度において税額が高くなることが予想された場合、自由に損失を計上できてしまうと、その事業年度に損失計上すれば税負担を抑えられます。その事業年度に発生した損失であれば良いですが、計上のタイミングを自由に操作して損失計上することは租税回避と呼ばれ、税法上、許されません。
税法上、損失計上ができるのは以下3つのケースです。
- 法律上の貸倒れ
金銭債権が法律上切り捨てられた場合 - 事実上の貸倒れ
状況から回収できないことが明らかな場合 - 形式上の貸倒れ
取引停止後1年以上経過した場合など
基本的な考え方として、回収の可能性が残っている場合には貸倒損失は認められません。督促などあらゆる方策を採っても回収不能である、ということが明らかである場合に、当該事業年度での損失計上が認められます。どの時点で回収不能になったのか、慎重な判断が求められます。
計上のタイミングを逃すと、その後損失計上の機会はありません。売掛金を回収できなかったにもかかわらず、売上に対する税金を負担したままの結果となります。
参考
No.5320 貸倒損失として処理できる場合|国税庁 (nta.go.jp)
関連記事
貸倒れと貸倒れ損失とは 対象となる債権もあわせて解説 | URIHO BLOG
貸倒損失とは 未回収の売掛金との違いと対策を解説 | URIHO BLOG
売掛債権の回収方法
売掛債権の回収は、企業にとって重要な活動の一つです。支払期日までに売掛金が支払われない場合、企業はその回収のために段階的な手続きを踏みます。ここでは、その一般的な流れとその各段階での具体的なアクションについて詳しく説明します。
メールや電話で状況を確認する
最初のステップは、債務者に連絡を取ることです。メールや電話を通じて、支払いの遅れの理由を確認し、支払いの見込みについて話し合います。この段階では、誤解や単純な忘れなどの問題が速やかに解決されることが多いです。
普通郵便で督促状を送る
メールや電話で解決しない場合、次に普通郵便で正式な督促状を送ります。この督促状には、未払いの売掛金の詳細、支払いを求める明確な要求、および一定の期限までに支払いがなされない場合に取る可能性のある次のステップについて記載します。
内容証明郵便で催告書を送る
さらに回収が進まない場合、内容証明郵便を使って催告書を送付します。内容証明郵便とは、送付した日付や送付した内容が公的に証明される郵便サービスです。内容証明郵便を用いることで、法的な手続きに移行する前の最後の通告として機能し、受取人が通知を受け取ったことを証明することができます。
支払督促、調停、訴訟等の法的手段をとる
それでもなお支払いがなされない場合は、支払督促、調停、訴訟などの法的手段に訴えることができます。支払督促は、裁判所に申し立てを行い、債務者に対して支払いを命じる手続きです。調停は、第三者が介入して双方の間で合意に至るよう仲介する手段です。最終手段として、訴訟を提起して法的に支払いを求めることが可能です。
関連記事
売掛金回収代行の解説 代行を利用するメリットと一般的な未回収が発生した時の流れ | URIHO BLOG
売掛金の回収と回収が滞った場合の対応方法について解説 | URIHO BLOG
時効の成立を防ぐ具体的な対策
売掛金の時効が成立すると、法的に回収が不可能となるため、企業は時効の成立を防ぐための具体的な対策を講じる必要があります。まず、回収方法と共通して定期的な債権の確認と督促を行うことが基本です。特に、大口取引先に対しては定期的な連絡を行い、支払い状況を把握しておくことが重要です。
もう一つの有効な方法は、前述した債権の一部支払いを受けることです。債務者から少額でも支払いを受けることで、債権の時効期間がリセットされます。また、債務承認書や支払計画書などの書面を取り交わすことも有効です。これにより、債務者が債務を認めたことが証拠となり、時効の主張を防ぐことができます。
まとめ
売掛金には5年の時効があり、債務者側が時効の援用をするとこで売掛金が消滅します。
売掛金を支払期日までに回収できるのが一番ですが、支払いが滞った場合、時効があることも頭に入れて督促の計画を立てる必要かあるでしょう。
売掛金の時効は、催告や支払督促、調停や裁判などを行うことによって、時効の進行を一定期間ストップすることや、リセットすることができます。一時的な中止を「時効の完成猶予」といい、リセットを「時効の更新」といいます。
売掛金が回収できず貸倒れとなった場合は、経理上「貸倒損失」として計上することで、利益や税金の額を低くすることができます。
売掛金保証サービス「URIHO(ウリホ)」は、取引先の倒産や未入金時に取引代金を代わりにお支払いするサービスです。事前に取引先に保証をかけておくことで、与信管理をしなくても安心して取引を行うことができます。また、督促業務に時間や労力を割く必要がなくなり、営業活動に集中することが可能です。
また、URIHOはすべての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用開始することが可能です。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。