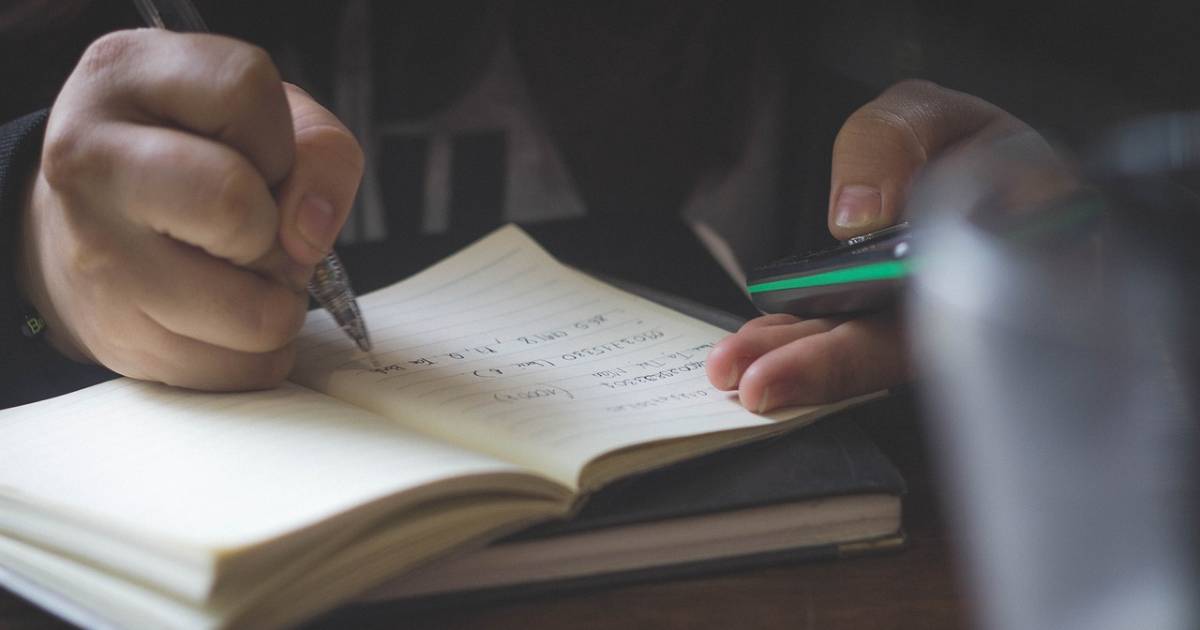企業間取引では掛け売りが一般的ですが、「請求書を送付したのに期日までに支払いがない」「何度も催促をしたのに入金されない」というような、売掛金が未回収になってしまうリスクもはらんでいます。
支払いが滞った場合には、「支払督促」を利用する方法があります。この記事では支払督促について、次のことを中心に解説します。
- 支払督促とはそもそもなにか
- 支払督促申立書とはなにか
- 支払督促申立書の記載項目について
支払督促の利用を考えている方にはもちろんのこと、そうでない方にも、社会人の基礎知識として知っておいていただきたい内容です。

支払督促とは?
支払督促とは、裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。
支払い督促は売掛金の未回収など、支払われるべき金銭が期日までに入金されない場合に利用できる手続きのひとつです。
まず期日を過ぎても相手方から売掛金の支払いが行われない場合、まずは内容証明郵便で催告書を送付するのが一般的な流れです。
それでも支払われなければ法的手段を検討することになるでしょう。
債権未回収の場合の法的手段としては、民事訴訟、少額訴訟、民事調停、支払督促があり、どれを利用するかは、状況に応じて選択することになります。
支払督促は裁判所に出向くことなく郵送だけで完結できるものですが、内容証明郵便の催促状などとは違い、法的効力を有します。
関連記事
催促とは 督促・催告の違いについてと催促をするタイミングについて解説 | URIHO BLOG
民事再生の解説 適用条件と取引先が民事再生手続きを行った場合の対応方法とは | URIHO BLOG
回収不能に至るまでのプロセスとは売掛金の未払いへの対応方法を紹介 | URIHO BLOG
支払督促の特徴
支払督促の特徴としては次のようなものがあります。
- 裁判所へ出向く必要がない
- 手数料が少なくて済む
- 強制執行を申立てることができる
支払い督促の利点は、裁判などの他の手段に比べて時間とコストを節約できることです。裁判所に足を運ばず、書類を郵送するだけで手続きができるため、労力としては幾分か負担が少なくすむでしょう。
また、手数料は訴訟の半額で済むため、経済的な負担も軽いです。例えば、請求額が100万円の場合、訴訟を起こすと手数料は10,000円かかりますが、支払い督促では5,000円です。
督促を受け取った相手は2週間以内に異議申立てをすることができます。しかし、異議申立てをしても支払いがない場合、債権者は強制執行を申立てることができます。
支払督促と少額訴訟の違い
支払督促と少額訴訟は、どちらも債権回収を目的としていますが、その手続きや適用範囲には違いがあります。
支払督促は、手続きが比較的容易であり、裁判所の審査も形式的です。異議申立てがなければ、督促は自動的に確定します。さらに、債権額に制限はなく、高額な債権にも適用される点が特徴です。
一方、少額訴訟は裁判手続きの一種であり、原則として口頭弁論が行われます。これは、債権額が60万円以下の場合に適用される手続きです。少額訴訟では判決が出るまでに時間がかかる場合もありますが、通常の訴訟手続きよりも迅速な解決が期待されます。
支払督促の流れと手続き
支払督促は次のような流れで進みます。
- 支払督促の申立て
支払督促申立書に必要事項を記入して、簡易裁判所に提出します。裁判所の窓口に直接持ち込まなくても、郵送で受け付けてもらえます。 - 支払督促の発付と送達
支払督促申立書に不備がなければ、支払督促が発付され相手方に送達されます。 - 仮執行宣言申立て
相手方が支払督促受領から2週間を経過しても異議申立てをしなければ、仮執行宣言の申立てをすることができます。 - 仮執行宣言の発付と送達
仮執行宣言の申立書に不備がなければ、仮執行宣言が発付され仮執行宣言付支払督促を相手方に送達されます。 - 強制執行の申立て
仮執行宣言付支払督促の受領後も相手方が異議申立ても支払いも行わなければ、差押等の強制執行の申立てをすることができます。 - 相手方が異議申立てをしたら訴訟へ
相手方が異議申立てをした場合は、民事訴訟の手続きに移行します。
参考:「お金を払ってもらえない」とお困りの方へ 簡易裁判所の「支払督促」手続をご存じですか? | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

支払督促の仮執行宣言とその手続き
仮執行宣言とは、裁判所が支払督促の手続きにおいて、債務者が異議を申し立てた場合でも債権者が直ちに強制執行を行うことを可能にするための宣言です。この宣言により、債権者は異議申し立ての結果を待つことなく、債権の回収を進めることができます。ただし判決が覆り、強制執行が無効になった場合は債権者は債務者に対して受領したものを返却しなければいけません。仮執行宣言の具体的な内容と手続きを以下に説明します。
- 仮執行宣言の申立て:
債権者は、支払督促の申立てと同時に、仮執行宣言の申立ても行うことができます。これは、債務者が異議を申し立てた場合でも、強制執行を行えるようにするためのものです。 - 仮執行宣言の発令:
裁判所が仮執行宣言を認めると、支払督促と同時に仮執行宣言が発令されます。この宣言により、異議申し立てがあっても、債権者は直ちに強制執行を開始できます。 - 異議申し立てと執行の停止:
債務者が異議を申し立てた場合、裁判所は執行停止を命じることがあります。しかし、債権者は保証金を供託することで、執行を続行することも可能です。
支払督促申立書とは?
「支払督促申立書」とは、支払督促の申立てをするときに必要な書類です。
支払督促申立書は、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に提出します。裁判所の窓口まで出向く必要はなく、郵送で提出ができます。
支払督促申立書のフォームは簡易裁判所で入手できるほか、裁判所のホームページからもダウンロードできます。
また、オンラインで申請ができるシステムもあります。
参考:
支払督促で使う書式 | 裁判所 (courts.go.jp)
支払督促申立書の記載項目の解説
支払督促申立書はフォーマットがありますので、決められた箇所に記載をしていけばよいですが、普段目にしないもののため、どのように記入するのかとまどうところもあるでしょう。
そこで、主な項目について簡単に解説します。
- 事件名
「請求事件」と書いてある左側に事件名を記載します。売掛金の請求なら「売掛金 請求事件」となるように、「売掛金」と記載します。 - 債務者
「債務者 は、債権者に対し」となっています。債務者が複数の場合には「債務者らは、連帯して 債権者に対し」となるように「ら」「連帯して」を書き加えます。 - 申立手続費用
支払督促の申立てにかかった費用です。債務者に弁済してほしい金額を書くのではないので注意です。費用は裁判所に問い合わせてください。 - 債務者の住所・氏名・連絡先
債務者の住所・氏名・連絡先を記載します。 - 簡易裁判所名
相手方の管轄の簡易裁判所名です。「〇〇簡易裁判所」となるように、〇〇の部分を記入します。 - 価額・貼用切手・収入印紙・葉書
請求する金額の元本を記入します。切手、印紙にそれぞれ収めた額を、葉書は相手に送達された結果の通知を受けとるもので、債務者が1名なら1枚です。 - 目録
2枚目の目録には、債権者、債務者それぞれの連絡先等を記載します。 - 請求の趣旨および原因
3枚目は請求の趣旨および原因です。請求額、手続費用、および請求の原因を記載します。書き方がわからない場合は最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。
関連記事
法人の債務整理とは?債務整理の種類を解説 | URIHO BLOG
債務超過と貸借対照表(バランスシート)の解説 赤字との違いもあわせて紹介 | URIHO BLOG
債権と債務の違い それぞれの言葉の意味と関係性を解説 | URIHO BLOG
まとめ
売掛金の未回収など、催促を行っても請求した金額が支払われない場合には、支払督促を申立てる方法があります。
支払督促を申立てるには、支払督促申立書を相手方の簡易裁判所へ提出します。その後相手方から異議申立ても支払いもなければ仮執行宣言申立て~強制執行申立ての流れになります。
支払督促申立書は見慣れない項目もあると思いますが、基本的にはフォーマットに沿って記入していく形です。
売掛金保証サービス「URIHO(ウリホ)」では、取引先の倒産や未入金時に取引代金を代わりにお支払いするサービスです。事前に取引先に保証をかけておくことで、与信管理をしなくても安心して取引を行うことができます。また、督促業務に時間や労力を割く必要がなくなり、営業活動に集中することが可能です。
また、URIHOはすべての手続きがWeb上で完結し、スピーディに利用開始することが可能です。売掛金の回収にご不安がある場合は一度導入をご検討ください。